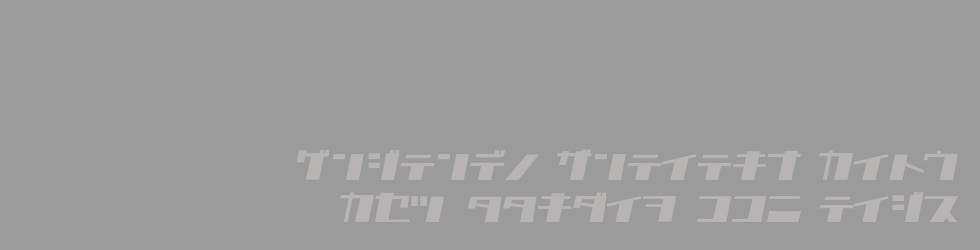愛と権威と後天的性格についての研究
愛 とは
「あなたの話をきちんと聞きます」という態度を示すこと。
相手のことをきちんと見つめ、耳をそばだてること。
この態度を感じたとき、人は愛を感じる。
具体的には「あなたという存在を認めます」「あなたを”私の主観的世界”における”構成要素の一つ”として認めます」という態度のこと。
愛を受けると、人は自信を持ち、元気を得ることができます。
愛を受けることができないと、人は自信を無くし、元気が出ません。
「愛」は態度を指す言葉ですが。
相手の気持ちや状況を読み取る「見立て」は、知識や経験が必要となる技術です。
一朝一夕では身につきません。
失敗しながら学ぶものです。
見立てを誤ると、その後の行動を誤る可能性があることは明白です。
権威 とは
多くの人に話を聞いてもらえる人、メディア(媒体)のこと。
権威になれば話を聞いてもらえるので、多くの「愛」を得たように感じます。
“定性的” な言葉。
しかし、「愛」と「権威」は異なる概念です。
本当は「愛」を求めていたのに、話を聞くという態度を欲し「権威」を求めてしまうこともあります。
権力 とは
「権威力」のこと。
具体的には身長、体重、お金、役職、肩書などです。
比較的、”定量的” な言葉。
肩書は、部下の数や年収などに置き換えて定量的に表現できます。
「金に溺れる」「地位に溺れる」というのは、愛と権威を誤解した結果です。
結局は、あなた自身が認められたのではなく、金や地位を求められているのです。
では、どうしたらいいのか。
まずはあなた自身が、愛を与えてください。
あなたの世界の一員として、周りの人を迎え入れてください。
そうすれば自然と、あなたも周りの人の世界の一員になれるでしょう。
所属集団 とは
家族や親戚、ご近所さん、学校、会社など。
生活の中で、所属する集団のこと。
所属集団は、生まれながらに決まっていることもあれば、成長(年齢や地域)によって変わることもある。また、契約(入学・入社・結婚など)によって変わることもあります。
所属集団は、一つとは限りません。
社会性 とは
所属集団への適応性・順応性を表現する言葉。
所属集団で、愛を得るための方法や手法を持っているか否かを表します。
あるいは、愛を受けれなくしてしまう要因を排除できているかを表します。
劣等感 とは
「どうせ愛を得られないだろう」と思いこむこと。
子供の頃は、自分の言い分を聞いてもらえないことがあり、生まれながらにして劣等感を感じることがあります。
また、所属集団を変えることや見識を広げた際に、すごい人を見て「この人には敵わない」と感じたときの防御反応として感じることがある。
「あのレベルまで人間は成長できるのだから、今以上に努力を積み重ねよう」や「漠然とした努力ではダメだ。質を上げよう」と考えること。
あるいは、「別の土俵を探して、自分の才能を活かそう」と思うことが正解。
しかし、自分が劣っているということだけにフォーカスを当て。
その結果、自分よりできない人を探して攻撃したり、自暴自棄になったりする。
具体的には、攻撃的な態度をとる。無視をする。質問攻めにする。弱者を装う。知識を披露する。腕力を披露するなど。
優越感は、劣等感の裏返しです。
アドラー心理学では、良い劣等感と悪い劣等感を分けて考えます。
しかし、すべて悪いものとしてとらえて問題ありません。
劣等感を基にした努力は、いびつな努力になります。
ケガや病気、社会的な軋轢の基になるため、悪いものとしてとらえてしまって問題ありません。
先天的性格 とは
生まれながらに持つ性格。
先天的性格は、まさに個性的です。
それゆえ、人と接する際に、邪魔になることもあります。
先天的性格そのままでは、社会との隔たりを感じてしまうこともあるでしょう。
後天的性格 とは
所属集団での社会性を得ようとするために学習した戦略。
社会性を獲得するために、先天的性格を包むオブラートのようなもの。
先天的性格のトゲを和らげるクッション材の場合にはそれほど問題にはなりません。
しかし、先天的性格を否定し、別の性格で上書きした場合、人生に息苦しさを感じます。
ローカルルール とは
ある特定の所属集団でのみ利用可能なルールのこと。
ローカルルールにのみ意味を成す「後天的性格」は、一般的な社会生活においては、不要であると言えます。
しかしながら、その事実に気づかず、かつ、そのルールに縛られているため、別の所属集団での生活に支障をきたしてしまうことがあります。
逆に、一般的には不要なローカルルールがあり、そのルールに気づいてないか、あるいは気づいていても実践することができない場合、これもまた生活に支障をきたしてしまいます。
このようなローカルルールに適応できないと、大きな心的ストレスを抱えることになります。
これを適応障害と呼ぶのだと思います。
このローカルルールのうちの一部は、リーダーの劣等感に起因するものが多くあります。
具体的には「どんな些細なことでも必ず報告しなくてはならない」など。
人の劣等感に付き合うと、愛を奪われることになります。
つまり、気を使わなくてはならない。
話を聞かなくてはならない。
注目しなくてはならない。
これはとても残念なことです。
自分自身の劣等感を捨てること。
そして、人の劣等感に付き合わないことが何よりも大切になります。
上記例に対する具体的な対策には「対面式の報告をやめ、一覧表を作りそこに書き込むことで報告の手間を減らす」など。
人以外への愛について
人以外に対する愛について考えてみると、利き酒が分かりやすいのではないでしょうか。
お酒がどのような味か、きちんと見つめ感じようとする。
また、それによってどのような印象を得るのか。
もちろん、間違ったらどうしよう、バカにされてしまうかも、などという劣等感は捨ててください。
この感覚は、絵画鑑賞、音楽鑑賞、映画鑑賞などでも同じでしょう。
そして、どのような印象や感情を持つか。
いいところや悪いところを批評的に探すのではないのです。
ただ単に、そういうところがあるということを知り、それをそのまま受け取るのです。
ぬいぐるみ や 植物 に愛を感じる理由
子供のころからぬいぐるみに相談している。
私の悩みはこの子がすべて理解してくれている。
なんていうのが、アニメなどのキャラクターでいます。
また、植物に対して、話しかけ。
しっかりと受け止めてくれるんです。愛があるんですよ。
などと言う方もいらっしゃいます。
しかし、本稿で述べた「愛」の考え方からすれば、何の違和感もない話になります。
当人が心を開いて、本気で聞いてもらおうとしている限り、それを否定するような言動をとらないわけですから。
愛を持っていると感じることになるのでしょう。
- PREV
- 絶対に失敗しない料理の思考法(極論かつ暴論)
- NEXT
- 満たされない想いとコップの水