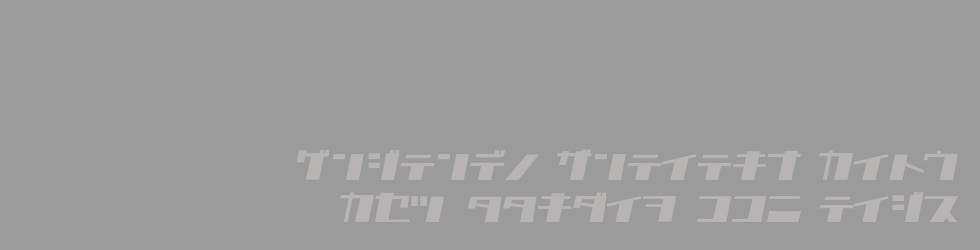ライヴハウス 学割論争に参加して
本稿は過去に掲載していたものを、サーバー移管に伴い、転載したものです。
日付は移管日です。
当時の公開日、更新日は忘れてしまいました。。
▼自己紹介
筆者:まっちょ
私は、20代後半からライヴハウスに行くようになった。
そして、ライヴハウスの魅力に感銘を受けると共に「こんなに素敵な場所に何故客が少ないのか?こんなに客が少なくて商売としてやっていけるのか?潰れちゃうのではないのか?」という危惧を抱いた。
そこで「現状」を知り、「問題点」を探り、「解決策」を提示することができればなぁと思うようになった。
現時点では、微力ながらも自分なりの手段で行動している。
将来的には、面白いことができればなぁと思いつつ、そのための情報収集とスキルを磨いている。
▼参加イベント詳細
【TITLE】
ライブハウスマン緊急集会・特別編 -ライブハウス学割論争-
【ACT】
打首獄門同好会 大澤会長
新宿アンチノック 印藤
O.M.K 牧瀬菊千代
司会:佐藤”boone”学
and more!!!!!!!!!
【DATE】
2012年8月30日(木)
【OPEN】
24:30
【START】
25:00
【INFORMATION】
数日前からtwitterを中心に色んな方の色んな意見が飛び散ったライブハウス学割論争。
その中心にもなった3名をお呼びして話を聞いてみようじゃありませんか。
USTREAM中継有り。
多くの方に参加頂きまして色んなきっかけになればいいなと思っています。
思い立ったら即行動。
面白そうな人には会いに行こう。
佐藤
四谷outbreak!スケジュールより一部抜粋。
ライブハウス学割論争のまとめはこちらから。。
Ustはこちらから。(回線が途切れたためにURLが分割されています。他のものはUst内「過去の番組」欄をご覧ください)(2015/04/02注:リンクが切れたようです。)
▼参加前に用意していた「答え」
「学割」をはじめとする割引制度は、ある層のターゲットを呼ぶための戦略だと思う。
それは赤字でもなんでもなく、「広告宣伝費(会計上は違うかも)」だと思う。
「学割」というのは、「もう少し金額が安ければ行ってもいい」というニーズを持つ学生にマッチさえすれば効果的な宣伝方法となる。
なので、そういうニーズのある学生を呼びたい時に使う『手段』であり、(ターゲットに対する)手段自体の是非を考えれば、否定する余地はない。
論点の一つとしてあった「誰がこの広告宣伝費を払うか」については、「誰がそういうニーズのある学生を呼びたいのか?」の回答となる人以外ありえない。
もろもろ考慮すると、今回の結論は「やりたい人がやればいい」の一点に集約される。
また、学生を呼ぶべきかどうかというのは、各人の判断に委ねられることだろう。
一般的な飲食店で考えてみよう。
大学が近く、お金のない学生がたくさんいることを知っていれば、その「学生を呼びたい」という気持ちを持つことはいくらでも考えられるだろう。
一方で、「大人の空間を演出したい」と思ったら「学生を呼びたい」とは思わないだろう。
どっちが良いとか悪いとかの問題ではなく、「どういう店にしたいか?」という想いの問題だ。
そういう意味では、今回の話には本来、対立軸なんてものは存在しない。
ただ、今回は「論争」というカタチになった。(タイトルがそうなっている)
論争になるからには、対立軸が存在するはずだ。
たぶん発端のツイートの言い回しなんだろうなぁと思ってた。
あるいは、些細な一言が、誰かの起爆スイッチになってしまうことだってある。
Twitterの怖いところは、いつも通りのTweetが本人の意志とは関係なく「社会に一石を投じる」ことになる可能性があること。
今回で言えば、「一石」のつもりが、まさに「爆弾」になってしまったことだろう。
何故、「一石」が「爆弾」になってしまったのか?
その原因には、ライヴハウスが抱える問題のヒントが、つまり解決策のヒントが隠されているのだろうと感じていた。
それを知りたいと感じ、今回のイベントに参加することにした。
▼参加後に感じた『答え』
何か提言を受けた際、腹を立てる人というのは、たいてい以下の2種類に分けられるのではないかと思っている。
・マジメにやっているのに「マジメにやれ」と言われた人
・とにかく楽したいのに「マジメにやれ」と言われた人
ライヴハウスに人が集まらないという現実を考えれば、後者が多いのだろうと思っていた。
ちなみに、「マジメにやる」というのは「努力する」でも、「考える」でも、適宜合う言葉に変換してもらえると嬉しい。
トッピングとして、「オレはやんないけど」がつくとさらに腹立たしい。
大澤会長がした今回の発端のツイートは「ライヴハウスは」で始まっているので、まさにこれになるだろう。
実際には、学割についてツイートする数日前に「バンド毎に行う割引というのは危険」というやり取りが行われていたことをお伝えしたい。
「ライヴで生計を立てていたあるバンドの前座が、割引してチケットを大量に捌いたために、本来入るはずの収入がそちらに流れた」ということが過去に起きたそうだ。そう考えると「ライヴハウスは」という表現になったとしても不思議ではない。
この「ライヴハウスは」は「主催者は」に置き換えることもできる。
これは大澤会長が「次回の主催イベントでは学割を行う」と明言していることも明らかだろう。
今回の企画に参加して驚いたのは、パネラーとして登場したライヴハウスの人が、皆とてもマジメに真剣にライヴハウスを運営していたことだ。
これはかなり想定外だった。
実際には、Ustで顔を出して、名前を名乗って、職場を出して、矢面に立つ覚悟のある人が不マジメであるはずがなかったのかもしれない。
そして、間違いなく、大澤会長のツイートが、そうやってマジメにやっている人に向けられたものではなかったということも想像できる。
大澤会長が終始居心地が悪そうにしている理由はそこだろう。
僕は、話を聞きながら「じゃあ、何故ライヴハウスに人が集まらないんだろう」と思っていた。
こんなにマジメに真剣に、志高く運営しているのに。。。
すると、アンチノック印藤さんの言葉が聞こえてくる。
「そんなに客が集まらないんですか?」
そうか。
様々な努力をして、その方向性が間違っていないライヴハウスには、きちんと客が入るのか。
それはすごく当たり前のことであると同時に、不景気の中、とてもすばらしいことだと思った。
それは、音楽を、ライヴを、ライヴハウスを求めている人が多くいることをあらわしていると感じた。
言い換えれば、業界として、集客が出来ていないのは
「努力の方向性が間違っている」か「努力していない」の2つに絞られるのではないかと思う。
ライヴハウスが抱える問題/解決策のヒントはここにあったのだと思った。
これで、今回の僕の目的は果たせた。
話は変わる。
一般的なお店であれば「集客商品」と「収益商品」というものがある。
たとえば居酒屋で「乾杯ドリンク100円」と銘打っているのは「集客商品」だ。
また、利益の上がりやすいものは「収益商品」だ。
ライヴハウスにとっては
「集客商品」=「バンド(チケット)」
「収益商品」=「バンド(チケット)」「ドリンク・フード」
となる。
したがって、ライヴハウスが収益を上げようとするならば、ドリンク・フードを売ればよい。
飲食店がしている努力と同じ事を、ライヴハウスがすればよい。
バンドにとっては
「集客商品」=「バンド(チケット)」
「収益商品」=「バンド(チケット)」「物販」
となる。
しかし、物販をたくさん売るというのは難しい。
これは、商品の企画開発の分野になってくる。
音楽の才能とはまた全く別の能力が必要だ。
AKB商法と言われるものは、ある意味では、この考えを最大限活かしたやり方だ。
しかし、これを実現するのは一般的には難しいわけで、結果的に
「集客商品」=「バンド(チケット)」
「収益商品」=「バンド(チケット)」
とせざるを得ない。
つまり、「このバンドを見たい!」という気持ちを「○○円までだったら払っていい」という言葉に変換し、チケット代を上げていくという方法だ。
バンドの価値が上がれば、必然的にチケット代は上がっていく。
言い換えれば、チケット代が、そのままバンドの価値になる。
これは、今回の論争の一つのポイントとなることだと感じた。
「チケット代がすなわち、バンドの価値」なのだ。
これに関する、異論は当然あると思う。
しかし、論争のポイントとしては存在していたと思う。
世の中はお金が全てではない。しかし、お金がないと出来ないことはある。
ライヴハウスを経営するにはお金が必要だ。
そして、バンドを続けていくのにもお金が必要だ。
「夢を売る商売」という言葉を考えれば間違いないだろう。
そう考えると、「チケット代を割り引く」という行為は「バンドの価値を割り引く」ことを意味し、反対する気持ちにもなる気がする。
本当の対立軸はここにあったのかもしれない。
ただし、これはあくまで、バンドにとっての話でしかない。
先ほども言ったように、ライヴハウスには「収益商品」=「フード・ドリンク」がある。
「フード・ドリンク」で収益を確保するのがライヴハウスの仕事であり、そのためのパートナーがバンドだと言える。
もちろん音響、照明etc.によって、「集客商品」の価値を上げるのも、ライヴハウスの大切な仕事だ。
バンドのみでは、「チケット代」がバンドの価値になる。
しかし、バンドとライヴハウスが協力すれば、「チケット代+フード・ドリンク代」をバンドに価値に変換することが出来る。
「バンドの価値」を「経済効果」という言葉に置き換えると分かりやすいかもしれない。
今回の論争の中では、この視点が足りなかったように思う。
そして、この視点が存在していれば、「割引」という方法に対する考え方も変わったのかもしれない。
- PREV
- 努力は報われるのか?
- NEXT
- ボトルネックを探し出せ