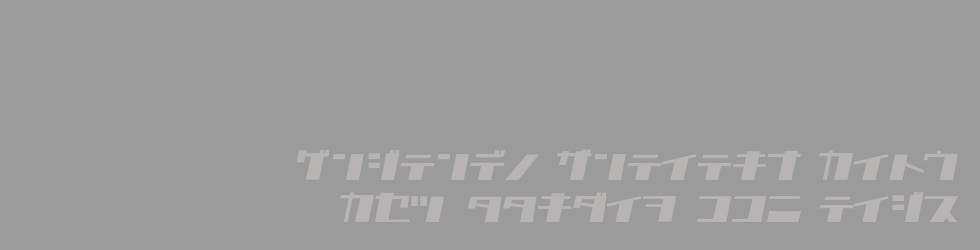言葉に囚われている
小林よしのり(マンガ家)×奥田愛基(SEALDs)――「対話」 | ぽこぽこ
この対談を読んで。
なんて冷静で頭のいいやりとりなのだろうと感じた。
なんだかんだで。
小林よしのりの書いた作品って『おぼっちゃまくん』しか読んだことないし。
SEALDsの活動も断片的にしか知らない。
だけど、これを読んでみると。
とても理性的で合理的で至極当然の行動を取っているよなぁと。
全体的にすごくいい内容で。
読んでいて本当に勉強になるのだけれど。
一点だけ気になることがあった。
それが、言葉に囚われすぎているって感じるところ。
会議もだいたいそうなんだけど。
言葉の定義をしっかりしないと失敗するんだよね。
話し合いにならない。
お互いがお互いに好きなことを言うだけになってしまう。
そんな中、学生側から「〝戦後民主主義〟っていう言葉を使う必要があるのか」という極めて鋭い質問(その実、提案)が出ている。
なのに、「私はそういう意図では使ってない。間違った使い方をしているほうが悪い」というスタンスで返答しているわけで。ここに年齢を重ねてきた人の弱みが出ているように感じた。
いや。年齢を重ねてきたからだけではないかもしれない。
絵と言葉で作品を作ってきた人の強みであり、弱みなのかなと思った。
もし、ここの部分が噛み合ったら。
この対談はどのように進んでいくのかが気になった。
本当に面白い未来を語ってくれたような気がしてならない。
あ、あと。もう一点。
小林よしのりのせいで今の日本がこうなったという意見についてだけども。
これは、まぁ、違う。
(小林よしのりの作品を読んでないから想像でしかないけど)きっと、未開の地に一本の旗を立てたんだと思う。
「こういう意見を持ってます!」と表明した。
一つの基準点を作った。それだけ。
でも、それを目印にして、同じだという人もいれば、「ちょっと違う!」と少しずれたところを指さす人もいた。
本当にただそれだけの話。
そこを中心にして、東西南北それぞれの方向に、好きなだけずれた場所を指さす人が出ただけ。
小林よしのりがしなければ、ほかの誰かがやっていたレベルの話。
(ただし、それが行われたのは10年20年後になったかもしれない)
その行動は、過去にここで『杭を打つ』と表現したこと、そのものだと思う。
それを謝る理由は全くない。
何故ならば、それ自体が悪いことではないから。これを謝る必要があるならば、もう何から何までも謝る必要が出てくるから。
というわけで。
今回は「言葉の定義をしっかりすりあわせてないと話が進まないんだよなぁ」の話でした。
- PREV
- 本物の世界を見ているか
- NEXT
- 自分の出方一つ